郡司和夫センセのデタラメ記事「コチニール色素」
毎度おなじみ、郡司和夫センセが「炎天下、祭りの出店料理は超不衛生で危険?蛾や虫が混入も…一部の清涼飲料水に毛虫の粉末混入」という、デタラメ記事を書いている。
前半は屋台の食品の衛生に関してで、こちらに関しては全く同感であるが、後半がいけない。
それから二十数年たちましたが、毛虫は相変わらず食品に混入しています。毛虫というのは、コチニール色素のことです。ジャムをはじめ、トマトケチャップ、清涼飲料水、冷菓、餡子類、水産練り製品などにオレンジ、赤、赤紫色を着ける食品添加物(着色料)として使用されています。毛虫の正体は真っ赤なエンジ虫のメスです。それを粉末状にしたものを年間50~60トン、中南米から輸入しています。
コチニール色素は、主成分がカルミン酸であることから別名カルミンともいい、古くから赤インキや日本画の絵具、繊維の染料、化粧品の顔料として使われていました。それが食品添加物としても使われるようになったのです。
揚げ足をとるようだが、エンジ虫は毛虫ではないし、虫の外観は真っ赤ではない。
毛虫は蝶類や蛾、特に蛾の幼虫で棘や毛のあるものをさすが、エンジ虫は別名コチニールカイガラムシで、カイガラムシの仲間である。
コチニール色素を採取するカイガラムシは、ラックカイガラムシ、ケルメスカイガラムシが主である。
これらのカイガラムシからコチニール色素が抽出され、莫大な利益を生み出した。
また、ラックカイガラムシが分泌する樹脂はシェラックと呼ばれる天然樹脂で、塩化ビニールが普及するまでレコード盤の材料として使われていたのは有名であり、現在でもワニスなどの塗料、ワックス材、医薬品の錠剤や錠剤状のチョコレートのつや出し剤として使われる。
コチニールカイガラムシやラックカイガラムシは養殖もされているが、多くのカイガラムシは害虫として嫌われる。
その理由は、植物に寄生して樹液などを吸い取り植物を痛めるが、表面に貝殻状の被覆物を持っていたり、体の表面に虫体被覆物と呼ばれる樹脂やワックスで覆われていて、農薬が非常に効きにくい事にあり、その処理が面倒であるからである。
カイガラムシ類
こちらのサイトを見ると、カイガラムシに手を焼いているのがわかる。
ちなみにこちらのサイトでツノロウムシの画像があり、裏側は気持ち悪い色をしていると書いてあるが、これはコチニール色素の色の成分であるカルミン酸の色である。
ツノロウムシからもコチニール色素がとれなくはないが、コチニールカイガラムシなどと比べて量が少ないため現実的ではない。
白い被覆物がワックスで、加熱すると溶け、その気になれば蝋燭なども作れる。
これに似たカイガラムシに、イボタロウムシ(イボタロウカイガラムシ、イボタカイガラムシ)というのがあり、このカイガラムシからはイボタ蝋という蝋がとれた。
イボタロウムシ
イボタ蝋
この蝋は融点が高く夏でも溶けないため、木材のつや出し剤や滑り材として使われ、以前は国内でも生産していたが、現在市販されているイボタ蝋は中国産と思っていい。
>コチニール色素は、主成分がカルミン酸であることから別名カルミンともいい~~。
これも間違っている。
カルミンはカルミン酸とアルミニウムまたはカルシウムとアルミニウムと結合させて不溶化した、カルミン酸のアルミニウムレーキ、カルシウムアルミニウムレーキの事で、カルミン酸とは別物である。
コチニール色素とカルミン酸は既存添加物名簿収載品目リストに収載されていて、食品添加物として使用できるが、カルミンは既存添加物リスト、指定添加物リストにも収載されておらず、食品添加物としては使用できない。
既存添加物名簿
一方、カルミンは「医薬品添加物成分の記載名称リスト」、「医薬部外品添加物リスト」には収載されていて、医薬品、医薬部外品、化粧品の着色料としては使用が認められている。
医薬品添加物成分の記載名称リスト
医薬部外品添加物リスト
なおカルミンは、欧米では安全な着色料として使用が認められていて、日本でも国際的整合性を図る目的で、食品添加物として指定することについて検討されている。
食品安全委員会への意見聴取及び食品健康影響評価結果について
食品添加物のコチニール色素には、カルミン酸が約15%含まれています。
毒性については、遺伝子を傷つける変異原性が強いことが、細菌を使った実験で確認されています。
石油を原料にしたタール系色素の食用赤色2号よりも変異原性は強いといわれています。
変異原性が強い(陽性)ということは、発がん性もあるというのが化学の常識です。
郡司センセや南センセの様なトンデモ系ライターはソースを明らかにしないが、確かに調べたところ細菌を使った実験で変異原性があるという報告はある。
微生物を用いる復帰突然変異試験
Yamaguchi(1988)の報告によれば、カルミンについての細菌(Salmonella typhimurium TA100)を用いた復帰突然変異試験(用量 0.12 mg/plate)では、代謝活性化系存在下で対照群の 2 倍を超える復帰突然変異コロニーの増加が認められたとされている。
(案)添加物評価書カルミン
一方、同じ文書内に次のように変異原性は認められなかったとの記述もある。
Ishidate ら(1984)の報告によれば、添加物「コチニール色素」についての細菌(S.typhimurium TA92、TA94、TA98、TA100、TA1535及び TA1537)を用いた復帰突然変異試験(最高用量 20.0 mg/plate)では、代謝活性化系の有無にかかわらず陰性であったとされている。
Arimoto-Kobayashi ら(2005)の報告によれば、添加物「コチニール色素」についての細菌(S.typhimurium TA98、TA100 及び TA102)を用いた復帰突然変異試験(濃度 10 mg/mL)では、代謝活性化系の有無にかかわらず、対照群の 2 倍を超える復帰突然変異コロニーの増加は認められていない。
また、添加物「コチニール色素」についてUVA を 4 時間照射(10±1.7 J/cm2)した上で細菌(S.typhimuriumTA98、TA100 及び TA102)を用いた復帰突然変異試験(最高濃度 10mg/mL)を実施したところ、代謝活性化系非存在下の TA98 の復帰突然変異コロニーが非照射時よりも増加したが、UVA 照射量との相関性は認められないことから、当該増加について Arimoto-Kobayashi らはアーチファクトであると考察している。
また別文書の「カルミン指定のための検討報告書」には次のような記述がある。
変異原性試験
(1)まとめ
カルミン(Carmine)については極めて限られた変異原性試験が実施されているにすぎない。
カルミンはカルミン酸(Carminic acid)のアルミニウム等のキレート化合物であることから、カルミン酸についての変異原性試験成績を合わせて記載することとした。
また、カルミンはコチニール抽出物と同じ原料(コチニール)から得られるものであることから、コチニール抽出物又はコチニール色素に関する変異原性試験成績も参照し、それらを含めて総合的にカルミンの変異原性について評価を行った。
カルミンについてはBacillus subtilis17A (Rec+)株及び 14T (Rec-)株を用いた DNA 修復試験(Rec-assay)が 2 試験行われ、いずれも判定不能の結果が得られている
また、Salmonella typhimurium TA100 を用いた、主に化合物の吸着に関する文献であるが、TA100 株/+S9/1用量のみの結果だけが記述されており、用量相関性や-S9 での結果等確認できない。~~以下略~~これらの情報を基にすると、カルミンについて変異原性の面から安全性を懸念すべき点は見出されていないと判断される。
カルミン指定のための検討報告書
コチニール色素、カルミン酸、カルミンに変異原性に関し特に懸念すべき点はないとしている。
発がん性にも触れている。
発がん性試験
まとめ
カルミンに関してはダヴィデ・カンパリ社より供給されたカルミン(カルミン酸含量:約50%)を経胎盤的に暴露した雌雄の児ラットに親動物と同様 50、150 及び500mg/kg 体重/日となるように混合した飼料、また、対照群として基礎飼料を最長で 109 週まで投与した試験が実施されており、対照群を含む各群で散発的に腫瘍が観察されたが、被験物質投与に起因した腫瘍の誘発は認められなかったと報告されている。
また、コチニール色素をマウスに 104 週間投与した試験が実施されていることから、これらの試験成績もカルミンの発がん性を推察する上で有用であると考え、参考資料とした。
コチニール色素(カルミン酸含量:29.8%)に関しては雌雄の B6C3F1マウスに 0(対照群)、3 及び 6%の濃度で 104 週間混餌投与した試験が実施され、被験物質投与に起因した腫瘍の誘発は観察されなかったと報告されている。
上記のラット及びマウスの試験成績からカルミン酸を主成分とするカルミンが腫瘍を誘発する可能性は極めて低いと考えられる。
カルミン指定のための検討報告書
発がん性に関しても、コチニール色素、カルミン酸、カルミンが腫瘍を誘発する可能性はきわめて低いとしている。
コチニール色素に関しては郡司センセは触れていないが、アナフィラキシーショックを起こしたとの報告がある。
天然赤色着色料でアナフィラキシー‐添付文書や外箱で注意喚起
これはコチニール色素やカルミン酸が問題なのではなく、不純物として残ってたコチニールカイガラムシ由来のタンパク質が原因である。
長い間原因となるタンパク質は不明とされていたが、CC38と同定されている。
コチニール色素中の夾雑主要アレルゲンタンパク質の解析に関する研究
添加物「カルミン」についてのアレルゲン性に係る試験成績について
高度精製コチニール色素やカルミン酸に関してはアレルギーの懸念はないとしている。
国内で精製されたコチニール色素はまず問題ないだろうが、輸入品に関しては少々不安はある。
なんでも食べる雑食性の人類が、エンジ虫のような毛虫を食用にしてこなかったのも、単に気持ち悪いという理由だけではなく、その毒性を数千年に及ぶ生活の知恵から会得、受け伝えられてきたからです。
毛虫を食品に利用するなんて、人類への冒涜ともいえます。
これに関しては、郡司センセの妄想としか言い様がない。
この記事にコチニールカイガラムシの画像があるが、せいぜい数mmの大きさで、表面には樹脂やワックスで覆われた虫は毒性云々より食用不適だったとしか言い様がない。
人類への冒涜とのことだが、カイガラムシは毛虫ではないし、人類はこれまで色々な昆虫類を食料としてきたわけであり、日本でもイナゴやざざ虫、蜂の子などは現在も食用にされる。
蚕のサナギも食用にされたこともあり、蚕は蛾であり幼虫は毛がないから毛虫という訳ではないが似たようなものであり、蚕を食うのも人類の冒涜とでも言うのだろうか?
この記事のタイトルもデタラメで、「・・一部の清涼飲料水に毛虫の粉末混入」などとあるが、コチニールはカイガラムシの粉末ではなく、抽出物である。
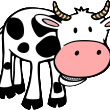






この記事へのコメントはこちら