渡辺雄二センセの非科学的記事「輸入柑橘類」
渡辺雄二センセの危険シリーズ、輸入柑橘類、『輸入オレンジやグレープフルーツ、危険な農薬検出→厚労省が食品添加物として次々認可』、という記事がある。
さてさて、輸入柑橘類は危険でしょうか?
現在、防カビ剤は、OPP(オルトフェニルフェノール)、TBZ(チアベンダゾール)、イマザリルなど、全部で9品目の使用が認められています。
いずれも、もともとは農薬として使われていたもので、危険性が高いのです。
>もともとは農薬として使われていたもので、危険性が高いのです。
農薬=即危険、というロジックだろうが、防かび剤に使用される物質は、いずれも毒物・劇物には指定されていなく、毒性はさほど高くない。
日本では収穫前に使えば農薬、収穫後は添加物として扱うという、制度上の区別であり、要は農薬だろうが添加物であろうが残留量が問題になるだけである。
日本では農薬も食品添加物も、安全性評価は食品安全委員会が行っていて、表題も「農薬・添加物評価書~」となっている。
今回、渡辺センセが触れている物質はいずれもポジティブリストに掲載されていて、国際的な安全性評価はされている。
厚生省が認可したとはいえ、OPPは農薬として使われていたものなので、その危険性を危惧した東京都立衛生研究所(現東京都健康安全研究センター)の研究者が、安全性を確認するために動物実験を行いました。
OPPを1.25%含むえさをラットに91週間食べさせたのです。その結果、83%という高い割合で膀胱がんが発生しました。
これは、OPPには発がん性があるということです。
オルトフェニルフェノール(別名2-オルトフェノール)はグレープフルーツによく使われている。
FAO/WHO合同残留農薬専門家会議(JMPR)の評価でも高濃度の長期動物で雄ラットの肝臓腫瘍や雄マウスの膀胱腫瘍が認められているが、ヒトに対しての発がんリスクの可能性は低いとしている。
以上から、本会議は、以下のように結論した。すなわち、2-フェニルフェノールに暴露された雄ラットに観察された膀胱腫瘍及び雄マウス観察された肝臓腫瘍に関しては、動物及び動物の性に特有なしきい値現象である。
従って、2-フェニルフェノールは、ヒトに対して、発がん性のリスクを有する可能性は低い。
この結論に関しては、本会議は、IARCが招集した作業部会による以下の分類について、認識していた。
すなわち、2-フェニルフェノール・ナトリウム塩は、グループ2B(人に対して発がん性がある可能性がある)及び2-フェニルフェノールはグループ3(人に対する発がん性については分類できない)。一日摂取許容量(ADI) 0-0.4 mg/kg 体重
ポジティブリスト制度施行に伴う暫定基準の設定された農薬、動物用医薬品及び飼料添加物に係る食品健康影響評価に関する調査報告書 オルトフェニルフェノール110ページ
ちなみに1.25%のオルトフェニルフェノールと言うことは、1kg中12.5g含むことになる。
オルトフェニルフェノールの残留基準は柑橘類で1kg中10mgであり、0.001%に相当していて残留基準の1250倍という、とてつもない量を投与した試験ということになる。
さらに1992年にはイマザリルが防カビ剤として認可されましたが、その経緯は信じられないようなものでした。
この当時、アメリカから輸入されたレモンについて、ある市民グループが独自に検査を行ったところ、農薬が検出されました。
それが、イマザリルだったのです。レモンが腐ったり、カビが生えないようにする目的でポストハーベスト(収穫後の農薬使用)として使われていたのです。これも法律に違反していました。
その際、厚生省は、なんとすぐさまイマザリルを食品添加物として認可してしまったのです。そのため、輸入柑橘類にイマザリルが残留していても、法律違反にはならないことになりました。こうしてイマザリルを使用した柑橘類が堂々と輸入されるようになったのです。
なお、イマザリルは動物実験の結果から、神経行動毒性を持ち、繁殖・行動発達を抑制することがわかっています。
量の問題であるとの指摘がある。
【目的】食品添加物の防カビ剤であるイマザリルについて行動発達毒性試験を行い,マウスの次世代の行動発達に及ぼす影響の有無について検討する。
【方法】イマザリルを混餌法によりCD1マウスに0(対照群),0.0006%,0.0018%,0.0054%となるように調製してF0世代の雌に妊娠期及び授乳期に投与して,次世代マウスの行動発達に及ぼす影響について検討した。
【結果】F0世代の授乳期の摂餌量が用量依存的に減少した。F1世代の授乳期における仔マウスの体重は雌の低濃度投与群で増加した。
また,授乳期間中の行動発達では雄仔マウスの4日齢及び7日齢の正向反射が用量依存的に抑制された。さらに雌仔マウスの7日齢の遊泳試験の方向が高濃度投与群で抑制され,14日齢の嗅覚性試行反応の経路が低・中濃度投与群で抑制された。F1世代の自発行動では移動時間が雄成体マウスの低濃度投与群で増加し,雌成体マウスでは低濃度投与群で抑制された。
また,雄成体マウスの一回あたりの平均立ち上がり時間が低濃度投与群で抑制される時間帯があり,雌成体マウスの立ち上がり時間が中濃度投与群で促進される時間帯が見られた。
【まとめ】本実験においてイマザリルの妊娠期及び授乳期投与により,次世代マウスの行動発達に対していくつかの影響が観察された。本実験で用いられたイマザリルの用量はADI値を基に算出された(0.0018%がADI値の約100倍相当)ものであるが,実際の人の摂取量はADI値の1/100以下であるので,現実的なイマザリルの摂取量では人に対して影響を及ぼさないものと思われる。
イマザリルの妊娠期及び授乳期投与によるマウスの行動発達に及ぼす影響
ADI(0.025mg/kg 体重/日)の100倍相当投与した場合に行動発達が抑制されたとされるが、実際のヒトの摂取量はAD1の1/100以下であり、ヒトに対して影響を及ぼさないとしてる。
次はチアベンダゾール
一方、東京都立衛生研究所では、TBZも危険性が高いと判断し、マウスに対して体重1kg当たり0.7~2.4gを毎日経口投与するという実験を行いました。その結果、おなかの中の子どもに外表奇形と骨格異常(口蓋裂、脊椎癒着)が認められました。つまり、TBZには催奇形性があることがわかったのです。
これも量の問題。
各種毒性試験結果から、チアベンダゾール(TBZ)投与による影響は、主に肝臓(肝細胞肥大等)、甲状腺(ろ胞細胞過形成等)、腎臓(腎盂移行上皮過形成等)及び血液(貧血等)に認められた。
繁殖能に対する影響は認められなかった。
遺伝毒性に関しては染色体の数的異常が認められたが、閾値を設定できるものであった。
発がん性試験において、ラットで甲状腺ろ胞細胞腺腫及び包皮腺腺腫の発生頻度増加が認められたが、これらの腫瘍の発生機序に遺伝毒性の関与は考えにくいこと、また仮に遺伝毒性機序が関連するとしても、その機序はチューブリンの重合阻害に基づく染色体の数的異常によるものであり、評価に当たり閾値を設定することは可能であると考えられた。各試験で得られた無毒性量について、用量設定間隔等を考慮して比較検討した結果、イヌを用いた1 年間慢性毒性試験並びにラットを用いた2 年間慢性毒性/発がん性併合試験、2 世代繁殖試験及び発生毒性試験の無毒性量10 mg/kg 体重/日を根拠として、安全係数100 で除した0.1 mg/kg 体重/日を一日摂取許容量(ADI)と設定した
ADI 0.1 mg/kg 体重/日
(設定根拠資料①) 慢性毒性試験
(動物種) イヌ
(期間) 1年間
(投与方法) カプセル経口(設定根拠資料②) 慢性毒性/発がん性併合試験
(動物種) ラット
(期間) 2年間
(投与方法) 混餌(設定根拠資料③) 繁殖試験
(動物種) ラット
(期間) 2世代
(投与方法) 混餌
(設定根拠資料④) 発生毒性試験
(動物種) ラット
(期間) 妊娠6~17 日
(投与方法) 強制経口
(無毒性量) 10 mg/kg 体重/日(安全係数) 100
農薬・添加物・動物用医薬品評価書 チアベンダゾール
チアベンダゾールは医薬品としては「ミンテゾール」(万有製薬)の商品名で腸管糞線虫症や旋毛虫症治療用の内服用駆虫薬として25~50mgkg 体重/日を経口で用いられたことがあった。
チアベンダゾール:ミンテゾール
次、フルジオキソニル。
まず2011年にフルジオキソニルが認可されました。
糸状菌に対して制菌作用があるため、防カビ剤としても使用が認められたのです。
しかし、マウスに対してフルジオキソニルを0.3%含むえさを18カ月間食べさせた実験では、高い頻度で痙攣が発生し、リンパ腫の発生率が増加しました。
リンパ腫はフルジオキソニルの投与に起因するものではないという研究がある。
ICRマウス(一群雌雄各60匹)を用いた混餌(原体:0,10,100,1000及び3000ppm:投与による18ヶ月間発がん性試験が行われた。~~略
~~3000ppm投与群では、耳介の紅斑及び保定時の痙攣がやや高い確率で観察されたが、対照群と比較して統計学的有意差は認められなかった。
3000ppm投与群の雌では、リンパ腫の僅かな発生増加(30%)がみられた。
より高量で実施された発がん性試験では癌の発生増加は認められず、この発生頻度は背景データの範囲内(13%~32%)にあった。
したがって、このリンパ腫は投与に起因する物ではないと考えられた。ADI 0.33mg/kg 体重/日
(ADI設定根拠資料) 慢性毒性試験
(動物種) イヌ
(期間) 1年間
(投与方法) 混餌
(無毒性量) 33.1mg/kg 体重/日
(安全係数) 100
ピリメタニル
さらに2013年にはピリメタニルが認可されましたが、ラットに対してピリメタニルを0.5%含むえさを2年間食べさせたところ、甲状腺に腫瘍の発生が認められました。
つまり、発がん性の疑いがあるということです。
腫瘍の発生はみとめられたようではある。
腫瘍性病変については、甲状腺ろ胞細胞腺腫が5,000 ppm 投与群の雄で9 例に、雌で7 例に認められ、雌の発生頻度は有意に高かった。
本試験において、5,000 ppm 投与群の雌雄で甲状腺ろ胞上皮細胞肥大等が認められたので、無毒性量は雌雄とも400 ppm(雄:17 mg/kg 体重/日、雌:22 mg/kg体重/日)であると考えられた。
農薬・添加物評価書 ピリメタニル
しかしながら、齧歯類での試験結果はヒトへはそのまま適用できず、ヒトへの発がんリスクは低いとの研究結果であった。
ラットの肝臓及び甲状腺に対する影響を評価するためのメカニズム試験の結果から、肝臓の酵素誘導による甲状腺ホルモンクリアランスの増加に起因する甲状腺ホルモンの不均衡によって、TSH 増加及び持続的な甲状腺刺激が起こることが示唆され、この持続的なTSH 増加がラットにおけるろ胞上皮の腫瘍の増加に関連していると考えられた。
げっ歯類では、甲状腺ホルモンの不均衡及びTSH上昇に対する感受性が特に高いため、この機序によるげっ歯類の甲状腺腫瘍は、ヒトへ外挿されないと考えられている。
本剤には遺伝毒性もないことから、ピリメタニルによるヒトへの発がんリスクの可能性は低いと結論された。ADI 0.17 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料) 慢性毒性/発がん性併合試験
(動物種) ラット
(期間) 2年間
(投与方法) 混餌
(無毒性量) 17 mg/kg 体重/日
(安全係数) 100
農薬・添加物評価書 ピリメタニル
アゾキシストロビン
また同じ年にアゾキシストロビンが認可されましたが、ラット64匹にアゾキシストロビンを0.15%含むえさを2年間食べさせたところ、13匹が途中で死亡し、胆管炎や胆管壁肥厚、胆管上皮過形成などが認められました。
発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び生体において問題となる遺伝毒性は認められなかった
1,500 ppm 投与群の雄の途中死亡動物(13 匹)では、投与に関連した変化として、肉眼的に総胆管の拡張、腹水、十二指腸膨満が、組織学的には総胆管の拡張、胆管炎、胆管壁肥厚、胆管上皮過形成がみられ、この変化に伴い肝臓で胆管上皮過形成及び胆管炎の発現頻度増加がみられた。
本被験物質の主要な標的臓器は胆管であると考えられ、雄のみに認められ、雌では胆管への影響はみられなかった。
本試験において、最高用量群の雌雄で体重増加抑制等が認められたので、無毒性量は雌雄で300 ppm(雄:18.2 mg/kg 体重/日、雌:22.3 mg/kg 体重/日)であると考えられた。
発がん性は認められなかった。C57BL/10 マウス(一群雌雄各55 匹)を用いた混餌(原体:0、50、300 及び2,000ppm)投与による2 年間発がん性試験が実施された。
2,000 ppm 投与群の雌雄では、体重増加抑制、食餌効率低下及び肝比重量増加がみられた。300 ppm 投与群の雄で体重増加抑制がみられたが、変動幅は大きくなく、増悪傾向がみられないため、毒性学的に有意であるとは考えられなかった。
いずれの投与群においても、病理組織学的所見に検体投与の影響はみられなかった。
本試験において、2,000 ppm 投与群の雌雄で体重増加抑制等が認められたので、無毒性量は雌雄で300 ppm(雄:37.5 mg/kg 体重/日、雌:51.3 mg/kg 体重/日)であると考えられた。発がん性は認められなかった。各種毒性試験結果から、アゾキシストロビン投与による影響は、主に体重(増加抑制)、血液(貧血)及び胆道系(総胆管拡張、胆管上皮過形成等)に認められた.
発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び生体において問題となる遺伝毒性は認められなかった。ADI 0.18 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料) 慢性毒性/発がん性併合試験
(動物種) ラット
(期間) 2年間
(投与方法) 混餌
(無毒性量) 18.2 mg/kg 体重/日
(安全係数) 100
最後にプロピコナゾール
また、今年になってプロピコナゾールが認可されました。
これも、もともとは農薬です。
マウス50匹に対して、プロピコナゾールを0.085%含むえさを18カ月間食べさせたところ、12匹に肝細胞腫瘍が認められました。つまり、発がん性の疑いがあるということです。
下記の850ppm投与の事を示しているのだと思う。
線種とガンは別物だが。
腫瘍の発生機序は遺伝毒性によるものとは考えにくく、閾値の設定が可能としている。
ICR マウス(一群雌雄各64 匹)を用いた混餌(原体:0、100、500 及び2,500 ppm)投与による2 年間発がん性試験が実施された。~~
~~腫瘍性病変として、2,500 ppm 投与群の雄において肝細胞腺腫(多発性)及び肝細胞癌(多発性)の発生頻度が統計学的に有意に増加した。
一方、同群の雌では、対照群との間に有意差は認められず、雌では発がん性は認められなかった。ICR マウス(雄、9及び53週中間と殺群並びに血液生化学検査群:一群10匹、発がん性試験群:一群50 匹)を用いた混餌(原体:0、100、500 及び850ppm)投与による18 か月間発がん性試験が実施された。
腫瘍性病変として、850 ppm 投与群で肝細胞腺腫(10/50 例)が試験実施施設の背景データ(3/50~9/50 例)を超えて発生し、また統計学的にも有意な増加であった。
肝細胞癌の発生頻度(2/50 例)は背景データ(4/50~8/50 例)の範囲内であった。
発がん性試験において、雄のマウスで肝細胞腺腫及び肝細胞癌の発生頻度増加が認められたが、遺伝毒性試験及びメカニズム試験の結果から、腫瘍の発生機序は遺伝毒性によるものとは考え難く、評価に当たり閾値を設定することは可能であると考えられた。ADI 0.019 mg/kg 体重/日
(ADI 設定根拠資料) 慢性毒性試験
(動物種) イヌ
(期間) 1 年間
(投与方法) 混餌
( 無毒性量) 1.9 mg/kg 体重/日
(安全係数) 100
ARfD 0.3 mg/kg 体重
(ARfD 設定根拠資料①) 急性神経毒性試験
(動物種) ラット
(期間) 単回
(投与方法) 強制経口
渡辺センセの言ってる有害事象は、安全性評価のため常識的な摂取量と比べとてつもない量を投与したケースである。
渡辺センセをはじめ、この手の記事の手口は情報のソースを公開しないと言うこと。
そして資料の都合の良いところだけ抜き出していかにも危険と思わせる手口である。
東京都健康安全研究センターでは、毎年市販されているオレンジ、レモン、グレープフルーツ、ライムなどについて、防カビ剤の検査を行っていますが、果実全体からはOPP、TBZ、イマザリル、ピリメタニル、アゾキシストロビン、フルジオキソニルなどがppmレベルで検出されています。
また、それらの防カビ剤は一部の果肉からも検出されています。
東京都の検査はかなり徹底していて、一部は果肉の部分だけ検査もしている。
食品衛生関係事業報告 平成29年版
下記は柑橘類の中でも取扱量の多い、オレンジ、グレープフルーツ、レモンを抜粋したものである。
なお、違反の検体は無かったとの事であった。
イマザリル
残留基準:ミカンを除く柑橘類、5ppm
オレンジ :果肉、3品中3品
最小値:0.03ppm 最大値:0.75ppm 平均値:0.28ppm
オレンジ :全果、33点中33点
最小値:0.03ppm 最大値:3.60ppm 平均値:1.50ppm
グレープフルーツ:果肉、4点中3点
最小値:0.03ppm 最大値:0.13ppm 平均値:0.09ppm
グレープフルーツ:全果、28点中、27点
最小値:0.08ppm 最大値:2.80ppm 平均値:1.10ppm
レモン :果肉、3点中3点
最小値:0.07ppm 最大値:0.13ppm 平均値:0.09ppm
レモン :全果、23中19点
最小値:0.03ppm 最大値:1.90ppm 平均値:0.99ppm
チアベンダゾール
残留基準:柑橘類 10ppm
オレンジ :果肉、3品中2品
最小値:0.04ppm 最大値:0.15ppm 平均値:0.10ppm
オレンジ :全果、33品中33品
最小値:0.02ppm 最大値:4.60ppm 平均値:1.29ppm
グレープフルーツ:果肉、4品中3品
最小値:0.01ppm 最大値:0.02ppm 平均値:0.017ppm
グレープフルーツ:全果、28品中23品
最小値:0.09ppm 最大値:2.20ppm 平均値:0.66ppm
レモン :果肉、3品中1品
最大値:0.3ppm
レモン :全果、23品中19品
最小値:0.01ppm 最大値:1.2ppm 平均値:0.42ppm
オルトフェニルフェノール(OPP)
残留基準:柑橘類 10ppm
オレンジ :全果、33品中1品
最大値:0.68ppm
グレープフルーツ:全果、28品中11品
最小値:0.26ppm 最大値:1.20ppm 平均値:0.73ppm
フルジオキソニル
残留基準:ミカンを除く柑橘類 10ppm
レモン :全果、23品中4品
最小値:0.77ppm 最大値:1.43ppm 平均値:0.793ppm
ピリメタニル
残留基準:ミカンを除く柑橘類 10ppm
レモン :全果、23品中1品
最大値:1.22ppm
圧倒的に検出量の多いのは、イマザリル、チアベンダゾール、オルトフェニルフェノール(OPP)の3種である。
最大値の場合と平均値で、どれだけ食べれば一日許容摂取量に達するか計算してみた。
七歳0ヶ月の男児(平均体重23.1kg)を対象に計算した。
イマザリル
一日許容摂取量:0.025mg/kg 体重/日
オレンジ果肉
残留量0.28ppm(平均値) 2.1kg
残留量0.75ppm(最大値) 770g
オレンジ全果
残留量1.5ppm(平均値) 385g
残留量3.6ppm(最大値) 160g
チアベンダゾール
一日許容摂取量:0.33mg/kg 体重/日
オレンジ果肉
残留量0.1ppm(平均値) 23.1kg
残留量0.15ppm(最大値) 15.4kg
オレンジ全果
残留量1.29ppm(平均値) 1.8kg
残留量4.6ppm(最大値) 500g
オルトフェニルフェノール(OPP)
一日許容摂取量:0.4 mg/kg 体重/日
グレープフルーツ全果
残留量0.73ppm(平均値) 12.6kg
残留量1.2ppm(最大値) 7.7kg
オレンジの果肉の最大値0.75ppmの場合で、一日770g以上食べ続けると健康上のリスクが上昇する可能性が有る事になる。
小学一年生が、毎日オレンジを770g食べる事はまず無かろう。
イマザリルより一日許容摂取量が一桁多いチアベンダゾールやオルトフェニルフェノールだと、大人でも食べれられない量となる。
ただし、柑橘類の場合皮ごと加工するマーマレードが有る。
オレンジ全果で、イマザリルの残留量3.6ppmの場合は、砂糖抜きの重量で160gでADIに達してしまうが、これだけ食べるとイマザリルの摂取よりも、糖分の過剰摂取の方が余程問題であろう。
実際にどれくらい防かび剤を摂取してるかだが、厚生労働省がマーケットバスケット調査をしてる。
平成 29 年度マーケットバスケット方式による酸化防止剤、防かび剤等の摂取量調査の結果について
アゾキシストロビン
1日の平均摂取量:0.00003mg/人/日
対ADI比 :0.0003%
イマザリル
1日の平均摂取量:0.00001mg/人/日
対ADI比 :0.0005%
オルトフェニルフェノール
1日の平均摂取量:0mg/人/日
対ADI比 :0%
チアベンダゾール
1日の平均摂取量:0.000026mg/人/日
対ADI比 :0.0004%
ピリメタニル
1日の平均摂取量:0.0000003mg/人/日
対ADI比 :0.00003%
フルジオキソニル
1日の平均摂取量:0mg/人/日
対ADI比 :0%
これは推定摂取量であり、例外もあるであろうが、このデータを見ても防カビ剤による健康リスクは非常に低いと思われる。
柑橘類はプロリンというアミノ酸を含んでいるが、カビの胞子の発芽を促進する作用があるため、柑橘類は低温でもカビやすい。
柑橘類に発生するカビには「カビ毒(マイコトキシン)」を産生する種があると言われ、きちんとリスク管理されている防かび剤より、カビの健康リスクの方が余程大きい。
輸入柑橘類の防カビ剤による健康リスクは非常に低いと思われ、どうしても気になれば国産を買えば良いだけの話。
毎度おなじみの自称科学ジャーナリストの渡辺雄二センセの、大山鳴動して鼠一匹すら出てこない、非科学的記事であった。




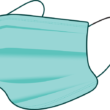



この記事へのコメントはこちら